「にほんブログ村」にエントリーしています。
できましたら、今日も問題を解いた後、ポチッとしていただければ、うれしいです。
激励のクリックをお願いします!
ご訪問ありがとうございます。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★過去問の到達度チェックにお役立て下さい★☆
⇒ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2013/test/mogitest.html
■ ≪過去問のみ模試≫ ■
□ たった300円で、現在のあなたの到達度がチェックできます。
気に入らなければ、お金はいただきません! by ホクベン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
≪7点アップ講座を今から受講する裏技≫
<クレアール>の短期講座より申し込めます
こちらから、どうぞ。
本試験全科目を、さっと見返すことのできる、ホクベン直前対策問題(解答・解説付き)ですが、下記の要領で、お譲りします。
バナーをクリックしてください。
さあ、今日から振り出しに戻り、労働基準法の1日1問です。
本試験までに、もう一回り出題するつもりです。
スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。
***労働基準法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の( a )以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2
使用者は、( b )以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数( c )ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(表は省略)
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、4割2、5割3、6割4、8割
(b) 1、6箇月2、1年 3、1年6箇月4、3年
(c) 1、6箇月2、1年 3、1年6箇月4、3年
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、8割
(b) 3、1年6箇月
(c) 2、1年
**********************
労働基準法第39条は、過去10年間で、H21を除く毎年択一式で出題されています。
選択式では、H22,H23に出題されています。
またH22には法改正もされています。
労働基準法<択一対策○×>
<平成23年 4A>
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★過去問の到達度チェックにお役立て下さい★☆
⇒ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2013/test/mogitest.html
■ ≪過去問のみ模試≫ ■
□ たった300円で、現在のあなたの到達度がチェックできます。
気に入らなければ、お金はいただきません! by ホクベン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
◇解説◇
休憩の3原則
1)労働時間の途中に与えなければならない
2)一斉に与えなければならない
3)自由に利用させなければならない 1)については、例外は存在しない。
そのため、使用者は労働者に対し、絶対に、労働時間の途中に休憩を与えなければならない。
2)については、例外が2つある。
一つ目は、労使協定の締結による一斉付与の例外である。この労使協定は行政官庁への届出義務はない。
二つ目は、法令による一斉付与の適用除外である。
運輸交通業や商業など8事業について規定されている。
3)の例外は、警察官や消防吏員などに該当する者については、休憩時間の自由利用の原則は適用されない。
これについても、法令上の適用除外である。
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
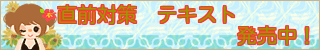
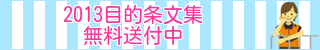

0 件のコメント:
コメントを投稿